血盟団事件の概要(3)
時代背景
当時の時代背景としては、次の4点を指摘できます。
まず、第一次世界大戦(大正3年~7年)による好景気にあった日本経済が、戦後は一転して不況に陥り、加えて大正12年9月の関東大震災が追い打ちをかけるように大きな打撃を与え、また昭和4年の世界恐慌に巻き込まれる等非常な難局にあったことがあります。
中小企業がバタバタと倒産し、街には失業者があふれ、労働争議、小作争議が全国各地に起こっていました。大学卒業生の就職率は1割ほどで、映画「大学は出たけれど」(小津安二郎監督)がヒットしたのがこの頃でした。
ことに農村の窮乏は深刻でした。
このような深刻な事態下にあるにもかかわらず、政界はいたずらに党利党略優先の政争に明け暮れ、内閣も次々に交替をするなど政情は安定せず、経済不況に対しても一貫した有効な手立てを講じられないままでした。そんな不安定な政情の下で、政党人や財界人の疑獄事件がしきりに起こり、国民の政治に対する不信と反感が強まっていました。
第一次大戦後、主要国の間では「軍縮」という流れが大勢となっており、ワシントン条約(1921~22年)での海軍主力艦に続き、新たに補助艦の建造をも制限するロンドン条約(1930年)が合意されました。しかし、これに納得しない海軍は、国会や枢密院に条約批准反対を働きかけましたので、国会や枢密院で政争の具に供されて紛糾しました。最後は、緊縮財政と軍縮を最大の課題とする政府側が、軍縮を歓迎する世論をバックに押し切りました。
しかし、陸・海ともに軍部には政党政治や軍縮に対する不満が残りました。
1917年に勃発したロシア革命の成功は、日本の思想界にも大きな影響を与えました。マルクス主義・社会主義理論に対する関心が高まり、やがて労働運動や農民運動と結び付き、労働争議・小作争議も頻発しました。
このような左翼思想の伸長に対して、国粋主義者や国家主義団体等の右翼が危機感を強くし、やがて国家の革新運動へと発展し、それが軍部若手将校たちへも浸透していき、その革新熱が高まっていました。
(後に血盟団のメンバーになる)農村青年たちは厳しい農山村の現状を実際に日常的に身を以って見、聞きしており、また、右翼学生たちは左翼思想の拡散、そしてこれに煽られた労働争議、小作争議の頻発に脅威を覚え、さらに陸海軍の軍人の大部分は農山漁村出身でしたので、農山村の窮状を歎き、娘達が売られ苦界に身を沈める悲劇に悲憤の思いを抱いていたであろうことは想像に難くありません。
「今の世の中をなんとかしなくては!」「国家を革新しなければ!」との想いを同じくするこれらの青年達を結びつける役割を担ったのが井上日召という人物でした。
井上日召について
(井上日召については、いろいろな本に書かれていますが、経歴については微妙に異なる点が多々あります。これは多くの本がいわゆる「孫引き」的な書き方であり、実際に戸籍等を確認したものあるのかどうか、あるとしてそれはどの本なのか分かりません。このことを予めご承知おきください。)

井上日召は本名を井上昭といい、明治18年(右の写真は護国寺にある日召の銅像です。銅像碑文には19年とありますが、18年とする本が多いです。)に、群馬県利根郡川場村の開業医の三男(四男とする本もあります)に生まれました。 長兄は父親と同じように医師となりました。川場村は三国山脈下の貧しい僻村でした。
学校が嫌いでいつも抜け休みをし、悪さばかりする井上昭は、親たちを閉口させ、村中の人を辟易させていました。内・外ともに悪童、憎まれっ子で、誰にも歓迎されなかったようです。
しかし、小学校の高等科に進むと、花の色、虫の声等見るもの聞くものことごとくが疑問の種になるようになり、次第に深く考え込む子供に変化したようです。一番最初の疑問は、「桔梗は紫で女郎花は黄色い、なぜだろう」というものであったといいます。(自著「一人一殺」、「血盟団秘話」(文藝春秋にみる昭和史)によっています。)
彼は明治38年旧制前橋中学を卒業後、小学校代用教員、陸軍補充兵、早稲田大学英文科とそれぞれを短期間づつ経て、明治41年に東洋協会専門学校(註:桂太郎によって1900年に創立された台湾協会学校を、1907年に東洋協会専門学校と改称したもので、現在の拓殖大学の前身になる。)に進みましたが、これも中退し、その後明治43年に満州に渡りました。
南満洲鉄道株式会社の社員となり、その裏では陸軍参謀本部の諜報業務に従事していました。第一次大戦の頃は坂西利八郎砲兵大佐(のちに中将)の秘書として中国各地を奔走していたり、商売をやったり、中国人と一緒に志那革命運動に参加したり、いわゆる「満州浪人」「大陸浪人」といわれるものの生活を送っていたようです。
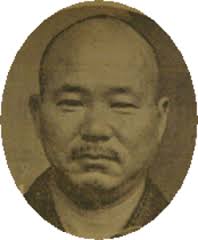
大正10年に帰国し、しばらくして故郷に戻りました。釣りや鉄砲撃ちにと無為の日々を送るうちに、子供の頃のような異常な精神状態がよみがえって、苦しみ始めるようになったため、明けても暮れても座禅行を続ける日々となりました。
大正12年の頃には、次第に不思議な現象をみるようになり、予見や病気治しができるようになり、遂には「開悟」し、積年の悩み・疑問が氷解したということです。(ここら辺りになると、神懸かり的な体験談になっていますが、自著「一人一殺」によっています。)
大正13年9月に「東南に向かって進め」という天の声に従って、上京。「日蓮上人の教義」(田中智学著)を読んで以来、日蓮上人に関する本を読み漁り、ついには日蓮宗総本山の身延山に登るも、意に満たず、東京に戻りました。
次第に、国内における社会主義者の増加、指導者階級の腐敗、右翼各派の主義主張、更には皇室中心主義に対する憂慮等、いずれの面からみても、現状のままでは放任することは出来ないと考えるようになり、まず自己の思想を確立するために静岡県下原町白隠禅師開基の松蔭寺で座禅修行して日蓮宗徒となりました。そこで日本精神に基づく国家改造の信念に到達したということです。
高井徳次郎と井上日召
昭和2年、交わりのあった右翼指導者や日蓮主義者に限界を感じ、愛想を尽かした井上は、静岡県三島の松蔭寺で禅の修行をしていました。その12月頃、旧知の高井が突然訪ねてきて、大洗に来てほしいと懇願されました。
(それより以前に、二人は千葉県木更津の鹿野山に道場を設け、青年を集めて訓育し、これを農村に派遣して、国家革新のための「大衆啓蒙」を行うという構想を練り上げ、田中伯を土地借用の名義人とすることの了解をも得ていましたが、結局資金集めに成功せず頓挫したという間柄でもありました。)
その際に、「旗マンダラ」を奉安する「奉安殿」もつくるということで、水戸の旧家・宇都宮高綱宅にあった「御国旗曼荼羅」と呼ばれる曼荼羅の寄附を受けていました。これは元寇の際に軍旗として使用されたとされ、神風を呼び寄せたという謂れをもつものでした。この時には、井上が預かっていました。
現物を何とかして拝みたいという人達がいるので、それを持って大洗に来て欲しいということでした。井上は、旗マンダラを奉持しつつ座禅修行をしていればいいくらいの気持ちで大洗に行きました。
しかし、高井は、井上には何らの相談もなく、井上が神秘的な霊力を有し、「病気治療」「加持祈祷」をよく行うと宣伝してあったのです。まぁ、だましうちにあったようなものですが、仕方なく引き受けているうちに、霊験あらたかと評判になり、大勢の患者が押し寄せるようになってしまい、修行どころではなくなりました。
そんなある日、高井に声を掛けられて田中伯を訪問すると、水浜電車がスポンサーとなって、大洗に明治天皇の銅像を安置する「明治記念館」と日蓮聖人の銅像を安置する「護国堂」を建てる計画があるという話がありました。そして、国家改造の基礎をつくるために護国堂で青年の指導養成を行う役を担うよう、田中伯から要請されました。
しかし、鉄道会社のための道具となることに疑問を持った井上は、これまでの病気治しにも懐疑的であったため、大洗を離れ、故郷・川場村に戻りました。
川場村に帰った日召のもとに、村の青年たちが押し掛けてくるようになり、直面している村の窮状をどうすればよいか訴えました。手始めに思い付いたのが炭焼きで収入を得、これを貯めて官有林の払い下げを受け、さらに炭焼きを拡張するという目論見でした。
これを実行に移し始めたその頃、またもや高井から、大洗に来て、出来上がった「立正護国堂」を管理し、国家革新運動の基礎づくりをしてもらいたいと言ってきました。故郷の炭焼きのこともあるので、極力拒否しましたが、結局は高井に押し切られてしまいました。
井上日召は、鹿野山で頓挫した道場の事業をここで行おうと意を固めました。ここに多くの青年たちを集め、これを自らが率いて国家改造の実行部隊とするという構想を練り、独りで護国堂での座禅修行をしながら、弟子となる青年たちが集まって来るのを待ちました。
やがて、煩悶を抱えた近隣の青年たちが徐々に訪れるようになりました。
こうしていよいよ舞台は整えられ、大洗の片隅で密かに動き始めたのです。